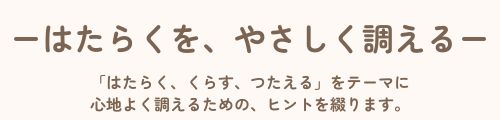片付けが苦手でもできる「大きな箱でざっくり仕舞う」収納のコツ

子どもの頃から、片付けが苦手だった
机の上はいつもごちゃごちゃ。
「あれ、どこだっけ?」と、いつも何かを探していました。
大晦日になると「今年こそは!」と大掃除を始めるのですが、気づいたら紅白が始まっている。
しかも、年内のゴミ回収日はもう終わっている──。
せっせとゴミをまとめていると、母から
「もっと早く始めてほしかった」と言われることもしばしば。
自分でも、「なんで私はこんなに片付けが苦手なんだろう」と思っていました。
外では「片付け上手」と言われて驚く
大学生のころ、カフェチェーンでアルバイトをしていたときのこと。
皿洗いのポジションに入ると、次のシフトの人から
「みきさんの後は、洗い場が整理されててやりやすい」と褒められたことがありました。
家ではあんなに片付けられないのに、なんで外だとできるんだろう?
と不思議に思っていました。
細かく決めても続かなかった「モノの住所」
一人暮らしをはじめた頃も、相変わらず部屋は散らかっていました。
でも、キッチンだけは、なぜか片付いている。
なるほど、「モノの位置が決まっていれば、戻せるんだ」と気づきました。
そういえば、カフェの洗い場でも、どこに何をしまうか決まっていました。
だから、私でも整理整頓できたんだ。
それ以来、家でも「モノの住所を決めよう!」と意気込んで、細かく収納場所を設定しました。
でも──うまくいかない。
「どこにしまったっけ?」と探すことが増え、結局また机の上が散らかっていく。
たとえば、
・お土産のキーホルダー
・「もう一度着てから洗濯したい」カーディガン
・ミニ家電の小さな取扱説明書と、謎の部品たち
これらの“住所が決まっていないモノ”が、机の上にどんどん積み重なっていきました。
どうやら、細かすぎるルールは私には合わなかったようです。
完璧な収納よりも、「戻しやすい仕組み」のほうが大事なんだと気づきました。
「大きな箱でざっくり仕舞う」に変えた
そこで、思い切ってルールをゆるくしました。
- 領収書 → 1年間、おなじ紙袋の中
- 「また使うかも」なもの → 無印のポリプロピレンの大きなボックスにまとめる
- 「そのうちメルカリで売りたい」もの → 別のボックスにまとめる
- 母子手帳・お薬手帳・財布などの大事なもの → 横広の引き出しにまとめて入れる
- 文房具 → 引き出しごとにざっくり分類+ラベルを貼る
このくらい「ざっくり」でいい。
そう思ってから、ようやく片付けが続くようになりました。
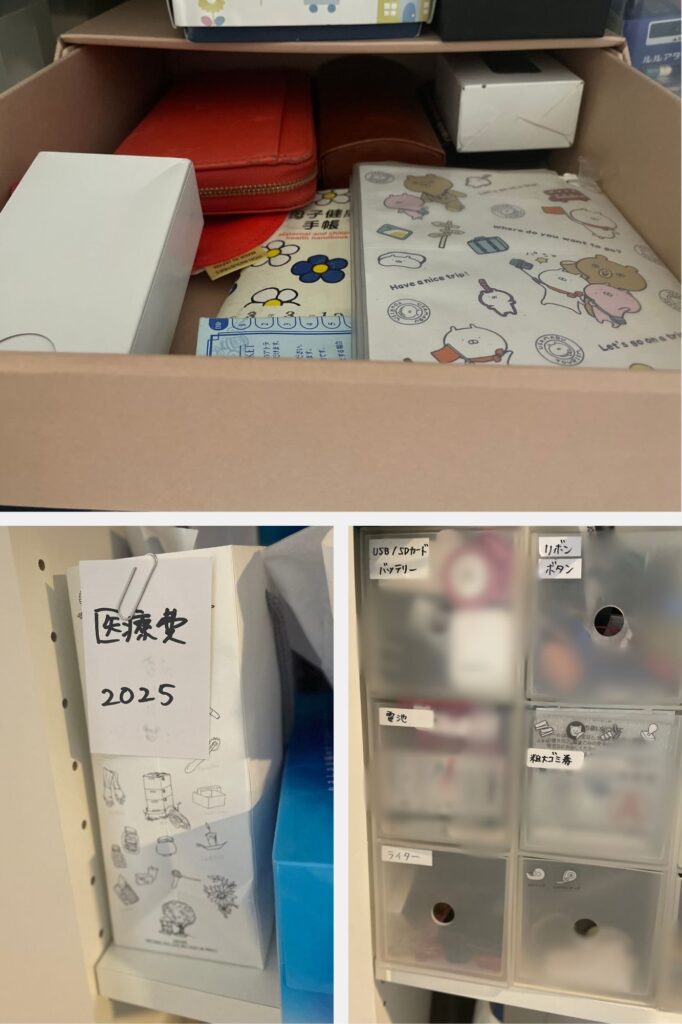
「とりあえず、この大きな入れ物に戻せばOK」
そう思えるだけで、片付けのハードルがぐっと下がったんです。
探すときも、「この箱の中には入っているはず」と見当がつくから、あちこち探す必要がない。
完璧ではないけれど、少しずつ“出しっぱなし”が減ってきました。
ざっくり収納で見えてきた変化
片付けを「完璧にやる」よりも、「戻せるようにする」ことを意識したら、暮らしが楽になりました。
机の上に多少モノが出ていても、「あの箱に戻せば大丈夫」と思える。
散らかってもリセットできる安心感が生まれました。
いまも、「住所が決まっていないもの」は机に散らばっています。
でも、昔のようにため息をつくのではなく、
「こういうカテゴリでまとめようかな」「どこに仕舞おうかな」と、ワクワクしながら考えている自分がいます。
焦らずに、少しずつ“ざっくりした住所”を増やしていこうと思っています。
「片付け上手」よりも「戻せる自分」
片付けが苦手でも、仕組み次第でちゃんと片付けられます。
「片付けられない私って、なんてダメなんだろう」なんて思う必要はありません。
コツは、ざっくりでも“戻せる場所”を作ること。
完璧じゃなくていい。
自分が気持ちよく続けられる形を見つけられたら、それが一番の「片付け上手」なんだと思います。
あとがき
昔は、片付けができない自分を責めていました。
人生で、どれだけ片付けのことで悩んできたか、わかりません。
でも今は、「ざっくり片付けできる」と思えるようになって、気持ちがずいぶん楽になりました。
完璧じゃなくても、できている部分に目を向けてみる。
そんな小さな変化が、暮らしを心地よくしてくれるのだと思います。
片付けが苦手な方に、「ざっくり収納する」という考え方が届いたらうれしいです。